
超勉強力
中野信子氏・山口真由氏著書の「超勉強力」を読了しました。東大卒のお二方の勉強にまつわるエピソードと方法論です。方や脳科学者、方や東大主席卒業。
まぁ、勉強がよくできる頭のいい方々です。
この年になって、今までの不勉強を反省しいろんな事を改めて勉強していますので、勉強が出来る方々のエピソードや方法論というのには非常に興味があります。
読み終わって分かったことは、お二方とも勉強することが好き、本を読むことが好き(というか国語力が高いので文字情報で知識を蓄える事が得意)ということ。
例えば、何かスポーツをやっていて上手くなろうと思ったら、できるまで何回も練習するでしょ?私達にとってその対象が勉強だったと本書に書かれている。
また、「ほとんどの勉強は国語力でカバーできる」と山口氏は語っていて、そのポイントは本の読み方にあるとワタシは受け取った。
山口氏の勉強方法論は以前に読書記録で書いたと思うが、「7回読み勉強法」。一冊の本を脳にスキャンしていくように7回読み込む方法。
参考までに過去記事置いときます。
対して、中野氏は本に「入り込む」読む方だ。小説だとイメージしやすいが、物語の登場人物目線に自分を入り込ませて、感情移入してしまうような読み方。
それを、あらゆる本で行う。本の内容を「自分事」にしてしまう。そうすれば、疑似体験として記憶に残りやすい。
なるほどと思うのだが、相当の読解力が必要なんじゃないだろうかと思うと簡単にはマネできなさそうと正直思いました。
後半はお二人の会話形式でページが進みます。読み進めていくと、なんというか幼少の頃から勉強するに適した家庭環境で、それに応えるように努力を続け結果を出してきた山口氏と、同じく勉強に適した家庭環境をベースに感覚的に勉強が出来てしまう天才肌の中野氏の勉強に対するアプローチの違いなどが垣間見ることができ、興味深かったです。
お二人が口を揃えて言うことは、「知ることは楽しい」。
知的好奇心を持ち続けることが勉強への第一歩。今の時代、わからないことや疑問に思うことがあれば手元にあるスマホで調べることができる。
つまり、人に質問をする前にほとんどのことは手元で解決してしまう。
ということは、人に質問をする時にはある程度の知識を持ってる事が前提となるわけだから、質問内容は「理解が正しいか否か」の建設的な議論でなければならないはず。
調べればすぐに分かるような質問は、誰かの言葉を借りると「ググれ、カス」と一蹴される世の中だ。
知識を増やすためにスマホを使うか、ゲームやSNSで消費するか。大きな差が生まれるんだろうな。
今日も最後までありがとうございます!ポチリとお願いします!めっちゃ喜びます! ![]() にほんブログ村
にほんブログ村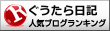 ぐうたら日記ランキングTwitterもやってます!フォロー大歓迎です!!
ぐうたら日記ランキングTwitterもやってます!フォロー大歓迎です!!
Follow @shidoiblog



